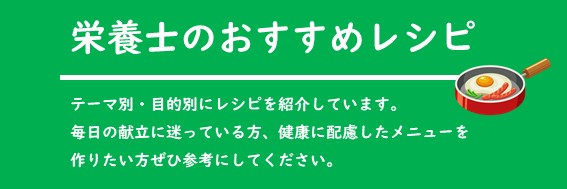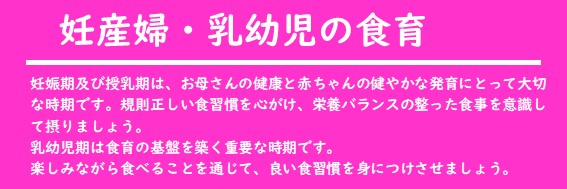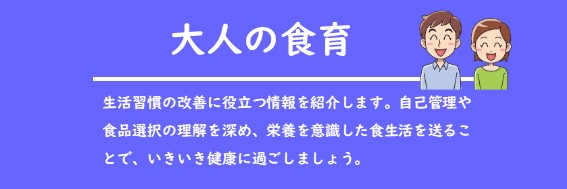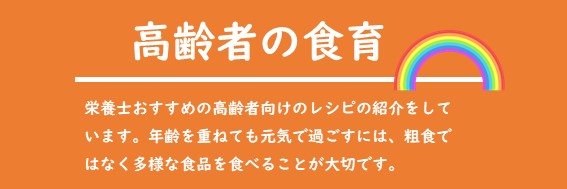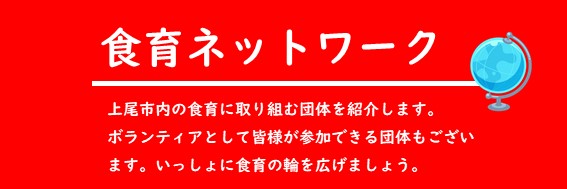食育ライブラリー
食育ライブラリーは食の面からみなさまの健康をサポートするためのサイトです。
ライフステージ別に、おすすめレシピや食の情報を掲載していますので、日々の生活にお役立てください。
掲載コンテンツ一覧(バナーをクリックすると情報に移動します。)
(⇒ 子ども家庭保健課のホームページに移行します)
栄養士が考えたレシピです。単品と1食があります。目的別で、ご活用ください。
単品は主食、主菜、副菜に分かれています。
1食の献立は主食・主菜・副菜が揃っていて、さらにエネルギー別や子ども向けのレシピなどテーマ別に分かれています。
1食の塩分が3g未満のレシピには減塩マークがついています。
(1)市内教育機関等の提供レシピ
保育所や学校では発育段階で必要な栄養素を栄養士が綿密に計算し献立を作っています。ぜひご家庭でも参考にしてください。
保育所給食編(単品)
小学校給食編(単品)
中学校給食編(単品)
(2)アッピーレシピ(単品)
アッピーレシピは上尾市健康増進計画・食育推進計画に基づき作成されたレシピです。
簡単かつエネルギーを控えた、さらに塩分も控えめのレシピを作成しています。副菜は野菜たっぷりのレシピになっています。
(3)テーマ別レシピ(1食)
カロリー別
500kcal以下 500kcal台 600kcal台 700kcal台
カルシウムたっぷりレシピ
子ども向け
正月料理
(4)埼玉県コバトンのレシピ
「埼玉県コバトン健康メニュー」は、健康を意識した食塩が少なく野菜の多いメニューです。おいしく健康づくりのできるレシピを紹介しています。
(1)健診結果から自分のカラダを知ろう
健診は、受けた後が大切です。
検査項目ごとに、生活習慣を見直すうえでのアドバイスを掲載しました。
ぜひ生活習慣の改善に取り組んでいただき、自身の健康管理にお役立てください。
健診結果を生活習慣改善につなげよう
健診を受けただけで終わりにせず、結果をよく見てください。検査値に異常があった場合、自覚症状がなくても放置すると悪化する可能性があります。検査項目ごとにアドバイスを紹介しています。ぜひご覧いただき日々の生活習慣の改善に役立ててください。
減塩レシピ
酸味や旨味、香辛料、香味野菜を上手に使うことで、塩分を減らしてもおいしく食べられるレシピを紹介しています。
免疫力を高めるレシピ
免疫力を高めるためには、主食・主菜・副菜がそろった栄養バランスの良い食事を基本に、十分な睡眠や休養、適度な運動が大切です。
腸内細菌を整え、免疫細胞の働きを高める食材を使ったレシピを紹介します。
災害時に備えた食事
災害時にどうやってご飯を作る?食事後のトイレは?いざというときに役に立つ情報をまとめたWebブックです。
高齢期は加齢によって筋肉などが「分解」されやすい時期です。年齢を重ねても元気で過ごすには、粗食ではなく多様な食品を食べることが大切です。ぜひ、語呂合わせ「さあにぎやかにいただく」で簡単にチェックしてみましょう。
(1)高齢期の食事
高齢期に栄養不足にならないために、何を気を付ければいい?必要な食品群を語呂合わせで覚えよう!
(2)シニア向けお手軽レシピ
食欲が落ちやすく、ちょっとしたことで体調を崩しやすい高齢期は栄養を十分に摂ることが大切です。
エネルギーとたんぱく質をしっかり摂れるお手軽レシピを紹介します。主食・主菜・副菜に分類しています。日々の食事作りの参考にしてください。
(3)フレイル予防レシピ(埼玉県)
市販のカット野菜、市販のお惣菜、レトルト食品を積極的に使って、できるだけ包丁やガスを使わずできるレシピを考えました。
もちろん、どの料理も味は保証つきです。
市内で食育に取り組んでいる団体を紹介します。
(1)食生活改善推進員協議会
地域で食生活改善に取り組んでいるボランティア団体です。
研修を受ければ誰でも参加することができます。ぜひ食育を通じて地域と繋がり豊かな食生活を一緒に支えてみませんか?
(2)食品衛生協会
飲食店が加盟し、自主衛生管理を実施しています。県の健康づくり事業にも協力し、健康づくり協力店として登録しヘルシーメニュー作りに取り組んでいます。